
カンボジアと言えば、国旗に描かれているアンコールワットで知られるが、20世紀に入るや政治、社会、文化の中心は首都プノンペンに移っていった。
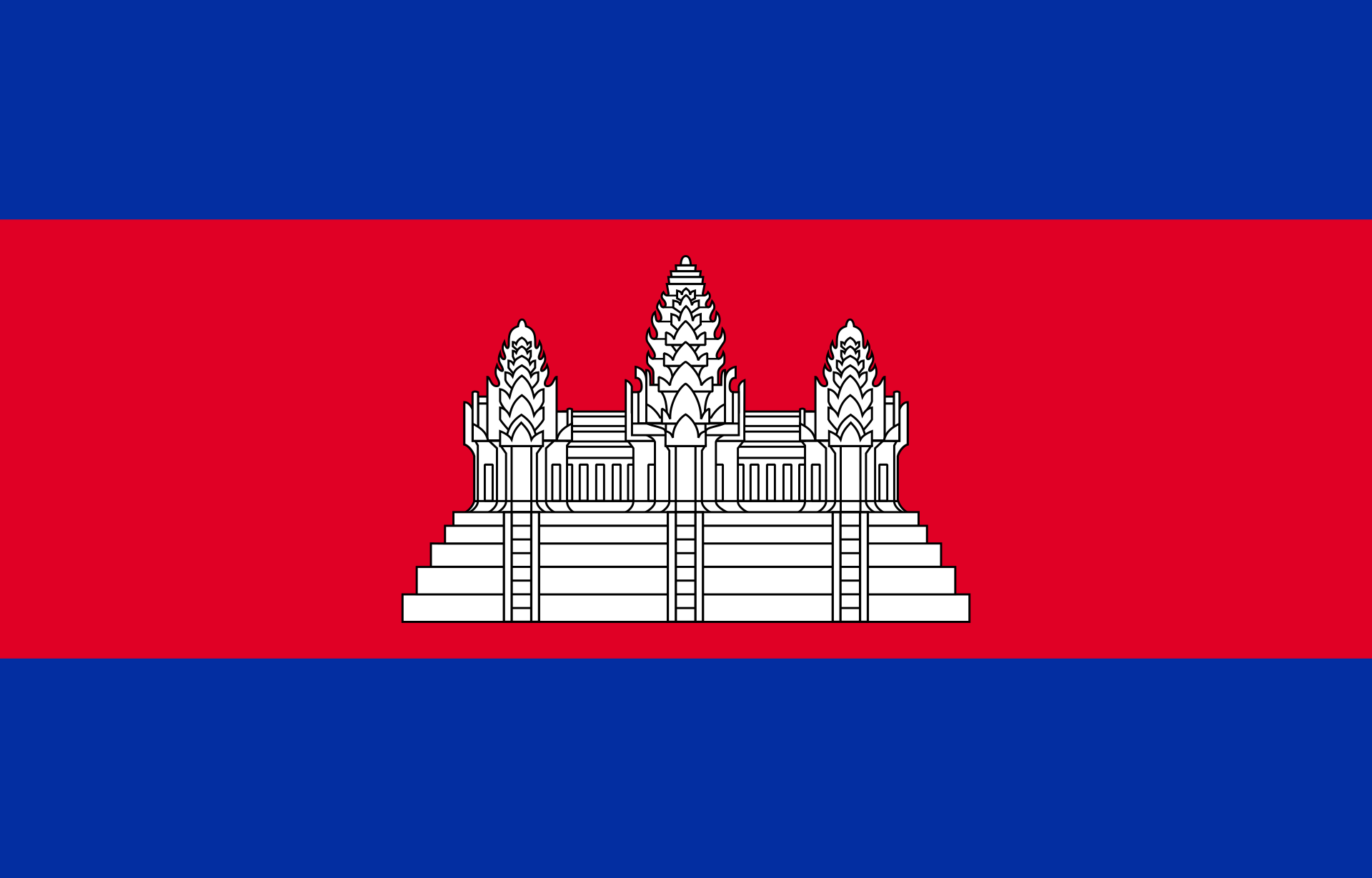
2000年代、シェムリアップの日系旅行会社の人は言っていた。「プノンペン観光といっても王宮、博物館とツールスレン収容所でしょ、プノンペンを目指す観光客は少ないんだよね。」と。確かに壮大なアンコール期の遺跡群は多くの観光客をひきつけてやまない。が、カンボジアの近・現代史に関心のある者ならプノンペンは外せない。それにプノンペン国立博物館には古代彫刻の至宝ともいうべき、第1級品が所狭しと並んでいる。実は遺跡好きならかならず立ち寄るところ、アンコール遺跡群の次に目指すところがプノンペンなのである。
プノンペンはフランスの造った計画都市
このプノンペンはフランス統治時代につくられた統治のための首都でフランス人の設計による人工計画都市である。
事実、1953年の独立後も首都プノンペンは圧倒的多数を占めるカンボジア農民にとってはよそよそしい街で、住民は官庁街のフランス人、市場(オールドマーケット)中心に中華系華人、そしてワットプノンの北側地区には旧下級役人や職人といったベトナム人、そして王宮付きのカンボジア人という棲み分けができていた。それはフランス統治時代から独立後の第1次内戦時代(ほぼ1960年代半ば~1975年)まで続いた。1960年代の書籍には、現在のガイドブックが謳い文句とする「美しいプチパリであった」とあるが、それはワットプノンや中央駅付近のフランス植民地官僚の住む地域を述べているに過ぎず、現在のオールドマーケット周辺の中国人街は道路のゴミの散乱、2階から水がぶん撒くといったかつての中国の地方都市の光景であったという。また、ウドンからプノンペンに王宮を強制移動させたものの、王宮の敷地内には王宮付きの奴隷や下級官吏、官女の掘っ立て小屋雅立ち、不衛生で見栄えも悪いとフランス総督の命で取り壊しと大掃除が行われたという話もある。そうしたこともあって、プノンペンの現王宮はフランス人が設計し、フランスの手によって造営された凝古典主義(カンボジア伝統様式を取り入れたレンガ積み漆喰造りの用法)的な近代建築である。隣接する現国立博物館はいっそうフランスの東洋趣味(オリエンタリズム)を表現した建物でその色彩にもその趣向が見られる。
フランスによる王宮建設自体がフランスによるカンボジア統治の意思であり、王室を監視下に置く措置であった。タイからすれば、カンボジアの宗主権をフランスによって奪われた形である。フランス総督府は、ワットプノンのそば(北東旧迎賓館、現・開発協議会の建物のある地)にあった。ここは第2次カンボジア内戦(1979~1991年)終了時の1991年、UNTACの本部にもなったところでもある。

ペン婦人がここで仏像を見つけ供養した伝説が持つプノンペン発祥地。丘の上のストゥーパ―(塔)は20世紀前半に建立。 古くから河川交通が盛んな時代、この丘は船乗りたちの目印になっていた。
フランスがカンボジア支配にために最初に拠ったプノンペンは、大きく蛇行するメコン、バサック川の合流する地(チャトムック)の右岸でワットプノンの小さな丘が眼につく河川の氾濫原でフランス進出当時は自然堤防上にりっちした小さな集落があるに過ぎなかった。アンコールワットの再発見者として知られるアンリ・ムオが訪れた当時のプノンペン付近は、自然堤防と氾濫原の後背湿地、散在する湖沼といった風景でメコン、バサック川には河イルカの遊弋やペリカンやサイ鳥などの大型鳥類の飛翔が見られた。

プノンペンに居を構えたフランスのカンボジア総督は1863年にフランス・カンボジア保護条約を結び(その前年、フランスはベトナムのグエン朝に迫り、カンボジアの宗主権を放棄させている、さらに1867年にはフランスはタイの王朝に迫り、カンボジアの宗主権を放棄させ、ノロドム王にはその前年、タイの脅威を説いてウドンから王都をプノンペンに遷都させた。そしてフランスのカンボジア植民地化の狙いは1884年に王の寝こみを襲って強要した新条約によって王の統治権を奪った。
ノロドム王を強要してカンボジアを保護下おいたフランスは、その拠点としたプノンペンの街づくりに着手した。王宮の建設もその一つである。

フランスは、一方でベトナムのグエン朝からベトナム南部を奪い、やがてカンボジア同様に保護下に組み込んだ。こうしてカンボジアは独立までフランス領インドシナの植民地の一つとなった。なお、カンボジアでの奴隷制度が廃止されたのは、フランス統治下の20世紀初めであった。また、王室内で隠然とした勢力を持っていたバラモン僧の顧問もこの時期に廃止された。言わば、カンボジアの近代化はフランスの手によって始まった。
フランスの歴史家には、シソワット王、モニヴォン王の時代をフランス統治=保護政策を円熟した平穏な時代で、近代化が始まると自画自賛しているが、実はコンポンチュナンの州知事パルデスが苛斂誅求で農民に暗殺されたり、各地での農民の抗議が起きたりとけして平穏ではなかった。
プノンペンの街―旧市街と新市街、そして現代化ー
プノンペンの街は「計画都市が造営された」フランス統治時代と独立後から一次、二次の内戦と復興期、そしてここ10年の現代化と3度、大きく変貌している。独立前までのプノンペンの姿は、雨季の時期や現在の道路の名から凡その姿が解る。

植民地時代
雨季になると熱帯驟雨でたちまち冠水する道路があちこちに見られる。そうした冠水場所をプノンペンの市街地図で青く塗れば、自ずから旧河川跡(河道)が辿れる。まさにこの地が大河の氾濫原であったことが解る。ここ5年、日本の支援で水道に次いで下水道改修作業が進み以前ほどではないが、それでも冠水地がそこかしこに発生する。例えば王宮前、川沿いのシソワット通りは冠水しないが、王宮前の道は冠水する。バサック川の現在の流路は新しく、そのため河川のつくる自然堤防がいかに幅細であるか、市街地もカンプチアクロム通りは冠水するがシハヌーク通りは冠水しない。都心部のボンケンコン地区も冠水する場所、しない場所にはっきり分かれる。

要は旧河川跡とその流路の自然堤防跡との違いからくる。ワットプノンから南に独立記念塔へ到る道(ノロドム通り)だが、中央駅から東に長方形の公園芝地がバサック川沿いに至る所と交わる場所に邪神(ナーガ)の欄干モニュメントが両側にある。ここはかつて橋がかかっていたことを記念したものである。東西に延びる公園の芝地はかつての河道で、フランス統治時代に埋め立てたてられた。
植民地から独立後、内戦と復興期
プサーチャ(オールドマーケット、旧市場=中央市場)とプサートマイ(新市場)という名称があるが、その名称とは逆に現在のプサートマイ(新市場)の対岸(旧河道の左岸)辺りに最も古い市(いち)があったのだろう。

次に街の主要道路の名前が王の名やクメール名なら旧市街地(カンプチアクロム)のあったところの範囲、独立後の道路ならソビエト通り、毛沢東通り、シャルルドゴール通り、金日成通りなど、内戦後には小渕通りまである。通り名の端を結んで円を描けば、独立後から2010年頃までの市街地が東の川岸を除いてて同心円状に拡がっていったことが解る。
2002.3年8月頃、熱帯驟雨(スコール)の多い年に空路でプノンペンを上空から眺めるとその姿は広い沼地に浮ぶ島(街)であった。プノンペンから放射状に延びる多くの道が市街地を出るやわずかな距離で消える、つまり水没しているのである。わずかに国道1~6号線のみが水没を免れている。要はそこだけは盛り土道路で水没を免れ、上空からはかぼそい堤防のように見えた。
カンボジアの風土を「南船北象」というが、アンコール期を除いて圧倒的に21世紀初めまで河川交通が優位を占め、そして命綱であった。
現代化の時期
2010年代、プノンペンの現代化が急速に進んだ。今でこそ都心部に高層ビルが立ち並ぶが。これらはいずれも2010年以降である。最も早く建てられたのがプノンペン商業銀行ビル、次にプノンペンタワービル、そして工事中断のままの韓国系ビル(韓国系ビルは、韓国内で詐欺罪が立件される工事中断、その後売却)、それ以降はべトナム系のヴァタナックビル(ペンギンビル 同様デザインのビルはホーチミンにある)、それ以外の事務所やマンションビルは中国系、ここ5、6年の建設ブームでの高層ビルである。

多くのカンボジア人には、長い間よそよそしい所だった
カンボジア人がプノンペンであふれるように増えたのは第1次内戦時代(1960年代末~1975年)の後期、米軍の爆撃やポルポト派の農村支配や戦火から難民として逃れてきた人たちにより。そうした人たちの多くが旧プノンペン市街の周辺部に集まり、貧民街となった。内戦期の初めにフランス・ドゴール大統領がカンボジアを訪問するが、その当時のフィルムに映るプノンペンで大統領を歓迎するカンボジア人の子どもたちのほとんどが裸足であった。
独立後、ベトナム人に変わって官吏に登用されるカンボジア人だが、その多くは中華系の血の混じったカンボジア人家系からである。悪名高いポル・ポトの本名が、サロットサル(白いサロット)であるようにポルポト政権時代の幹部のほとんどが色白のフランス留学生帰りで近親関係にあったものが多い。ポルポト、ヌオンチア、キューサムハン、そしてツーレスレン刑務所(後に虐殺博物館となる)の所長も明らかに中華系の華人の血は色濃く混じっており、独立時代には超エリートたちであった。
あまり知られていないが、ポル・ポトはコンポントム州の華人家系の出自、従妹と姉が相次いで当時モニヴォン王の愛人(お手付き)ー後宮入りーとなったため、姉に呼ばれて少年期を王宮で過ごしている。その意味では、王宮こそカンボジア近・現代史の舞台である。
ポルポト時代の農業中心の国土大改造計画の強制労働も、その荒唐無稽さは留学生エリートたちの幼少時からの農民生活の無縁さと無知、カンボジアでは特権層の子弟という出自からきたものである。色の白い者(ネアック・ソウ)たちがネアック・トム(お偉いさん)、ネアック・ミエン(お金持ち)が特権を占め、色黒の純クメール族農民(ネアックスラエ)を見下し君臨する世界が長く続いていたのである。プノンペンがクメール人で多数派なるのは、第1次内戦期(1970-75年)の混乱と、ここ30年に過ぎない。

現代化=急速な発展とそれがもたらす歪さ
こうしたプノンペンの急速な発展=現代化だが、一方でプノンペンは歪(いびつ)な姿を見せている。都心部の高層ビルや周辺部の工場進出の多くは外国資本(特に中国資本)であって、自前の経済発展がもたらしたものではない。ここ10年のプノンペン市街地の急速な拡大は、地価の高騰とともに周辺部に貧民街をドーナツ状に押し出していった。貧民街の多くは街中や周辺の低湿地帯にあり、雨季には未舗装の道は泥濘の道となるところである。そうした所に多くの貸家、長屋、アパート家屋が立地し、農村からの出稼ぎ労働者の受け皿となっている。そのことがより明瞭に表れたのが2021年のコロナ禍の4月であった。
2021年4月、コロナ禍第3波でプノンペンがロックダウンされた時、プノンペンの感染ホット地域(レッド、オレンジゾーン)に指定されたところは、都心部近くに取り残された貧民街やプノンペン都をド―ナツ型に囲む周縁部の劣悪な環境の工場と住宅(貸家、貸し部屋アパート、長屋が多い)の混在地域であった。そうした地域は、コロナ禍がなくとも毎年流行するのデング熱の猖獗地でもある。










