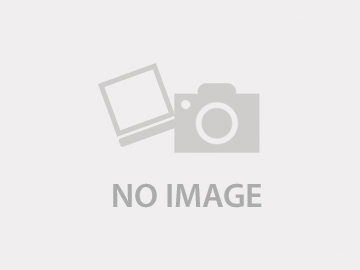海外旅行で初めて訪れた国で、そこに王宮があったら先ずは見学したほうがいい。王制であってもなくても過去に王がいれば、たいていは王宮がある。王宮を見れば、その国の歩みや国力、文化の高みなど漠然としたものであれ、ひと通りのこと理解できたり、感じるものがある。
タイの王宮はバンコクのチャオプラタヤ河畔にある。かって「水の都」と言われたバンコクは運河が街を縦横に走っていた。今は街中の運河のの多くが暗渠や埋め立てられ、街中で今も水上交通に利用されている運河はたった一つであるが、旅客や通勤客の足としてボートが走っている。
バンコクの王宮は高い塀に囲まれ内部は見えず、敷地も広い。わずかに王宮内の建物の屋根の重なりと高く聳える黄金色のストゥーパ(仏塔)が窺えるだけである。また、かつてタイの王朝と覇を競ったビルマ(現ミャンマー)の旧王宮は古都マンダレーにあり、一辺が約3km濠(ほり)を周囲にめぐらせ、濠の幅70m、その内側は高さ8mの城壁で周囲を囲んでおり、鬱蒼とした森の中心部に戦火で焼失した王宮の建物が復元されている。そして次にベトナムだが、古都フエにあるグエン朝の王宮も敷地も広いが、タイやミャンマーにその広さは及ばない。グエン朝は、その後期になってようやく現在のベトナム領域を統一したが、王宮はまさに小中華帝国の趣である。北京の紫禁城にその規模、意匠、壮大さや豪華さでは遥かに及ばずない。そしてビルマはイギリスに、ベトナム・カンボジアはフランスの支配下に入り、わずかに英仏の間隙を縫ってタイだけが独立を保った。それ故か、タイの王宮や付属寺院(ワットプラケオ)は、その規模、凝った意匠、豪華さを最もよく示している。そしてカンボジアの王宮だが、まことにささやかで、塀も低く、防御という点はほとんど考えていないのがわかる。

ベトナムから船でメコン川を遡り、プノンペンに着いて初めて河岸の王宮の佇まいを望んだ時、何とも可愛げな王宮でお伽の国に着いたかのような気持ちになったことを覚えている。


カンボジアの王宮はその小ささだけでなく、その歴史も浅い。事実、フランス統治下にフランス人によってデザインされ彼らの近代工法で造られたものである。
旧都ウドンからの遷都
かつてプノンペン北方のウドンにあった王都がプノンペンに遷都したのは、タイから圧迫を恐れた王室とそれを好機に保護下に置こうとしたフランスの思惑から、旅の案内書には王自ら望んで遷都したかに書かれているが、そんな状況ではなかったようだ。歴史的背景を見るにフランスが強要したとかに思える。

1866年に王都ウドンからノロドム王が正式に遷都した時は、カンボジアは長くタイ、ベトナムに両属する形の半独立状態で、前王のアンドゥオン王は1853年、そうした状況を打開しようとベトナムを圧迫していたフランスに保護を求めるため密使を送り、そのためタイの怒りを買っていた。
ノロドムが王に就いたのは1859年で、それを機に遷都した。もちろんフランスの後ろ盾を当てにフランスの誘いに乗ったものだ。元々ノロドム王と次のモニヴォン王は幼少期にタイ王家の人質としてバンコクで暮らしていた。両王共に日常会話はタイ語であったと言われている。クメール語でも王家独特の言い回しで、土着のクメール農民に通じるものではなかったようだ。そもそもウドンでもプノンペンでも王都でのクメール人の居住は王宮の廷臣か奴隷で市場の主は華僑たちであった。
遷都の初め、現在の地に造られた王宮は木造であった。初めこそ友好を演じていたフランスだが、やがて牙を剥く。1884年、ヴトナムからサイゴン(現ホーチミン市)含む南部地域を奪い支配下に収めたフランスは、王宮前の河岸に砲艦を停泊させ、インドシナ知事トムソンが早朝王宮に乗り込み、寝ぼけ眼の王に迫り王家の統治権をフランスに譲渡させる新条約に署名させた。まさに西欧の悪名高い恫喝外交(砲艦外交)そのものであった。ここにカンボジアはフランスによって主権を奪われた。
フランスはそのインドシナ領の一角カンボジアで植民地経営を始め、ベトナム人を下級役人の登用してカンボジア人には苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)で臨んだ*。そのため地方勢力の抵抗や農民の蜂起も起きている。一方でフランスは王制の維持に努め、王家の内部までは概ね干渉しなかった(王家の奴隷廃止やバラモン僧の後見の廃止はフランス勧めであったが)。こうしたフランス式植民地経営はベトナムのグエン朝、ラオスの王朝に対する姿勢と同じで、ここにその後のインドシナの悲劇の歩みが始まるのである。結果としてベトナム、ラオスの王制は滅び、カンボジアのみ国連主導で大国と近隣国の同意の下に1992年に立憲民主制として王制が残った。
*このフランス式植民地経営、実務としてカンボジア農民に苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)を執行したのがベトナム人であったため、今なお残るカンボジア人のベトナム人への反感はこれがために生まれた。フランスから見れば、使えないクメール族でベトナム人を使ったほう何かと便利で、ベトナム人の移住すら奨励、黙認していた。
先ずは即位殿とシンメトリーの庭へ

現在の王宮は、失意のノロドム王に没後に王弟のシソワットが王に就いた時代に完成したものである(1919年)。王宮はフランス人建築家の設計によるもので外観は擬古典主義(カンボジア伝統様式を取り入れた)の近代建築で工法はレンガ積みの漆喰塗りの建物である*。四方を壁に囲まれた王宮の東正面の門が「勝利の門」、ここは現在、王や首相、外国から賓客のための門になっている。一般の見学者は南東部壁面に開けられた小さな入口から、出口は少し南の先にある。ここから銀寺(シルバーパコダ:王室付属寺院)と王宮を囲む壁の間を通り、王宮の前庭に出る。王宮の多くはシンメトリー(左右均衡)が一般的である*。敷地中央に東向きの建物が主殿である即位殿、その左手(南側奥)王の執務の宮殿、手前に宝物倉、南東部の建物は宴会ホールである。

*東南アジアの国々レンガ積み漆喰塗りの西洋建築をガイドブックではコロニアルなんて言う言葉で持て囃す風潮があるが、コロニアルとは植民地風という意味である。
*日本の王宮も中国文明の影響が濃い時代はシンメトリーの建物配置だが、中国の影響が少なくなるとシンメトリーが少なくなり、雁行や渡り廊下で繋ぐ建物配置に変化していくといった。どうやらシンメトリーや威圧的な建物は日本人の感覚に合わなくなってきたのだろう。
場違いな感、「ナポレオン3世の館」
王宮の敷地に入るや主殿(即位殿)が先ず眼に付くが、次に場違いな西洋建築(これは「ナポレオン3世の館」と名づけられている)に驚く。

この館の由来はナポレオン3世(1852ー70年在位)の帝政期に皇帝の妻であるユージーヌ王妃からシソワット王に送られたものという。洋館を贈った当時、皇帝は絶頂期と自負していたのであろうが、1870年に敵軍の捕虜となる不名誉で帝政は崩壊した。その形見となった感のある建物だが、フランス支配下のカンボジア王家はそれを大切に保存し現王宮に移築した。背景になじまないその建物にその異様さ感じる人もいる。即位殿の右手前の小さな建物は象舎である(現在、象はいない)
主殿(即位殿)


先ずは即位殿を見学しよう。基壇を高くした即位殿の内部を見るに中央奥に王座、天井は織り上げ式天井で仏画が描かれているが西洋の画法で、仏画でなければ、ベルサイユの宮殿の一間である。装飾の意匠はまさに近代フランス式の宮殿である。即位殿の右手奥、壁に隔たれた横長の建物は王の私的空間で見学できない。

ポルポト政権期(1975-79年)、当時シハヌーク夫妻と二人の子ども(下の子が現国王)がこの建物に軟禁状態であった。シハヌーク国王の回想記に「恐怖だったのは銃を持って少年の警護兵たちだった。気まぐれに鳥や小動物を射撃する。その銃がいつ自分たちに向けられるかと思うと気が気ではなかった。」とある。政権末期(1978年)、ポルポト政権の軟禁状態であった元国王を取り込もうと、ベトナムは十数人の決死隊を王宮に送り込もうとしたが、ポルポト派兵士の発見により全員が河岸で死亡した事件が起こっている。それほどに王宮としては侵入容易と見られていた。
現在の国王シハモニ殿下の即位はこの主殿(即位殿)で行われ、公的には皇太后と私的空間の建物に居住していると言われるがほんとうかどうか定かではない。前国王のシハヌーク殿下は、和平後も王宮に居住することは少なく、北京にある中国が用意した殿下用の宮殿で過ごす期間が長かった。暑いカンボジア、宮殿と言えどもコロニアルな建物は快適ではなかった感がある。即位殿の背後は拝観不可の森でプノンペン随一の深い森であろう。
「ナポレオン3世の館」にはフランスから送られた洋服や宝飾品などが展示されているが、概して見るべきものは少ない。帰路は隣接の王室付属寺院:銀寺に向かう。
王室付属寺院:銀寺(シルバーパコダ)


銀寺は愛称で本堂の床に銀タイル5329枚(約20㎝四方)が敷き詰められているところから生まれたという。正式の名称はヴァット・プレア・カェウ・モロコット(エメラルド寺院の意味)である。この寺は創建当時(1892-1902年)は木造・レンガ積漆喰塗り建物の寺院であったが、大理石の支柱やテラスなど、1962年再建の現代工法の再建である。再建の時期の1962年は、前国王のシハヌーク殿下の時代でベトナムの戦火に遠く、内戦が深刻化する前の中立・非同盟を標榜する殿下の絶頂期で出あった。エメラルド仏を擁する本堂やその他建物、回廊は現代工法とはいえ、その意匠は王宮同様に擬古典主義のデザインでタイ寺院建築のような極彩色や色タイルの使用は少なく、重なる屋根の勾配も緩やかで奇怪な守護神の巨像もなく、落ち着いた優美な印象を持つ。
黄金の宝冠仏とエメラルド仏
本堂は東が正面とし、その内部にはシャンデリアが吊るされ、中央奥に黄金の宝冠仏を安置する。その黄金の宝冠仏は重さ90kg、最大25カラットのダイヤや2086個の小粒のダイヤで飾られている。この仏像はシソワット王が先の王ノロドム王の遺言によって造ったものという(1904年)。その背後に仏舎利を納めた箱を挟んで仏殿があり、そこに寺院名の由来となったエメラルド仏が鎮座する。タイのバンコクにある王室付属寺院ワットプラケオは黄金の宝冠を頂くエメラルド仏が本尊として知られており、奥殿のこの仏像が本尊であるように思える。また周囲には小仏像や各国や高僧から贈られた宝物が並べられている。

境内には本堂南に人工の丘は聖山カイラスを模したもので頂の祠には仏足石がおかれている。本堂右手(北)の建物(図書館)には仏典、本堂後ろ(西)にはアンコールワットのミニチュア、そして歴代の王のストゥーパ(仏塔)や前国王シハヌークの娘「王女のストゥーパ」などが建てられている。


また回廊には北から壁画が「ラーマーヤナ」の叙事詩の物語が描かれている。この壁画風雨に晒され、かなり古びて見えるが再建時に描かれたものである。よく見ると、様式に則った絵であるかのようだが、顔の表情や構図を見るにかなり稚拙で遠近法がおかしく歪んで描かれている。もちろん、伝統様式であろうが、タイでの同類の壁画を見ている者にはその稚拙が否応なく見えてきてしまう。同じ画家の壁画は国内にここ銀寺を入れて3か所のみである。


プノンペンの王宮と付属寺院:銀寺はバンコクのそれと及ぶべくもないミニチュア版であり、国力の差は歴然としている。それでいてこの銀寺の境内、タイのワットプラケオの絢爛さや煌めきを欠くが、妙に落ち着く心に優しい佇まいである。銀寺の境内はいつ行っても綺麗で緑も多い。境内に置かれた色とりどりの熱帯花卉が見えるのもいい。カンボジアには元来、造園という感覚も伝統はない。ベトナムには中国の影響で造園や庭を鑑賞して楽しむ伝統があるが、どうもカンボジアより西にはなさそうである。美しい熱帯花卉もいずれも鉢植えを置いたものである。

この銀寺、1979年にベトナム軍に追われてポルポト政権が崩壊し、占領したベトナム軍が本堂床の銀の板を剥がし、持ち去ったというエピソードがある。

伝統衣装という名のモデルさんだが、こうした姿の晴れ着が表れたのフランス統治時代の富裕層から、それが庶民の訪問着になったのはやっと21世紀からである。カンボジアのガイドの語る愛国主義的説明はショービズム(扇動的な愛国主義)に近く、言わばポルポト派を断罪しながら同様の創られた歴史である。
王宮・銀寺見学の最後に博物館や美術館巡りの終わりくるミュージアムショップに当あたる一角に来る。そこで奏らられる伝統音楽は農村の寺院で奏でられる音楽であり、伝統衣装は王宮の官女の19世紀末以来の服装であり、足踏み式織物は伝統的といっても絣(かすり)のみ織り方のみ。要は農村手工業である。さらに絹と言えば日本の西陣の職人出自の方が桑畑から養蚕まで復興した織物が唯一である。ここで見られる織物そのもは、ポルポト時代にほぼ全滅したなかで生き乗った女性たちの伝わったものである。ここで見られるもの、聞こえるクメール伝統文化とはアンコール栄光と何ら関係ないものである。14世紀以降、全く振るわなかったのがカンボジアの歴史である。

上の座像はカンボジアではよく見かける像(レプリカ)である。国立博物館所蔵のジャヤヴァルマン7世像として知られている。写真後ろに地図があるのは、クメール人が夢想とともに語るカンボジア・ジャヤヴァルマン7世の栄光時代の最大領土地図である。それだけこの王の以後、カンボジアの歴史は振るわなかったことを物語る。文化的な伝統として今に残ったものはほとんどない。古代の石造や煉瓦積遺跡以外に現存する伝統寺院で100年を超えるものは国内でわずかに2カ所である。文化としてアンコール王朝期につながるのはわずかに農民の歌舞(今も田舎での盆や正月に踊られるロアムヴォン=輪踊りの類)だけであったろう。アプサラダンス自体、60年ほど前に王家の女性による創作ダンスである。それ以前、舞踊と言えば王室歌舞団は専らタイ舞踊であった。手織り絣(かすり)が銀寺をでたところで実演されているが、絣の伝統的な文様もタイに残っているものとほとんど変わっていない。
*王宮・銀寺 案内図

*王宮・銀寺の位置